今日はデフリンピックのお話です。
ご存じの方も多いと思いますが、デフリンピックは国際的な「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」で、「東京デフリンピック2025」が開幕しましたね。
デフリンピックはパラリンピックより歴史は古く、今回で100周年の記念すべき大会だそうですね。(日本では初めての開催とのこと。)
普通のオリンピックと何が違うかといえば、聴覚に障害があるだけなのでルールは普通の競技に準じているんですが、たとえば合図の方法がスタートのピストル音のかわりにランプの点滅や審判が旗で合図をするなどでするようです。もちろんコーチや選手感のやりとりも手話やゼスチャーです。
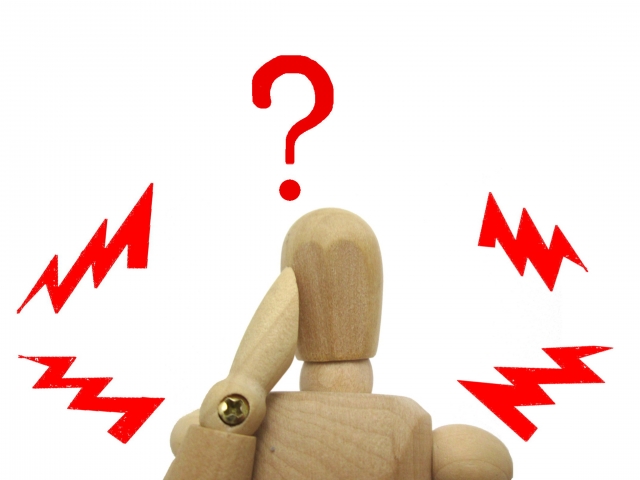
音が聞こえない選手たちが、目で見て肌で感じ全身で表現するパフォーマンスがどんなものなのか?私はテニスをやるのですが、意外と音って大事で、相手が打ったボールの摩擦音やバウンドした音て球種や距離感を図ったりしています。
それが聞こえない中プレー、一見聴覚障害が不利なように思えますが、実はデフリンピックの選手たちには静寂の中だからこそ、感じ取る世界があるんだろうなと思います。
静けさの中でこそ、生まれる集中やつながり、それはまさにヨガ八支則の第5段階にあたるプラティヤハーラ(感覚の制御)の実践だと思いました。
プラティヤハーラ(感覚の制御)
私達の日常は五感の刺激で溢れています。
スマホの通知音、絶え間なく目に入ってくるテレビやYoutubeなどのニュース、その他街にあふれる香りや味覚など、知らず知らずのうちに五感が心に波を立てているんです。
じゃあどうすればいいのか。。。。感覚機能をオフにすること。
ヨーガ・スートラでは「まるで亀が甲羅の中に手足を引っ込めるように」感覚器官が対象となる外部刺激から撤退すること、と表現されたりもします。
例えば私達は耳を閉じることは難しいですが、呼吸法や瞑想で目を閉じて呼吸を感じてみるとか、鏡を使わずに自分の感覚に意識を向けると目から入る視覚情報を取り入れないことになりますね。
またレッスンで自分の出来を周りの人と比べなくなることは、プラティヤーハーラの鍛錬が進んでいる、ということにもなります。
とはいっても無理に「外界をシャットアウトする」のではなく、外に向きがちな意識を、そっと内側に向け、内なる声を聞くつもりで。1・2・3・4・5
静けさの中で、私たちは本当の自分を思い出す。それが、プラティヤハーラの知恵です。
今日はデフリンピックをイメージしながら、私達の神経系にとっての「深呼吸」をして、
静けさの中で、本来の自分を見つめてみましょう。
これからも思いつくままブログを更新していきますのでまた来て下さい。
つれづれなるままに・・・
ツナガルYOGAは、西東京を中心に活動しています。 パーソナルトレーニングの他にヨガのグループレッスンなどご希望の場所へ出張も承ります。初回は無料ですのでお気軽に試してみませんか?








